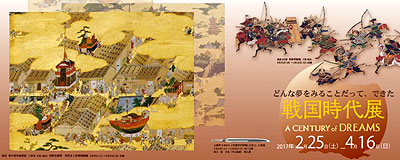大阪府大阪市の 大阪城天守閣 では、3・4階展示室において テーマ展 「桃山のTAKUMI -意匠・技巧・工匠-」 を開催、 【刀 銘)(三葉葵紋)以南蛮鉄於武州江戸越前康継】 【脇指 銘)出羽大掾藤原国路】 【脇指 銘)於大坂和泉守国貞作之】 など、たくみを凝らした桃山美術の優品87点を展示します。 「戦国乱世から泰平の世へ日本の歴史が大きく転換した時代、16世紀の中葉から17世紀の初頭ころまでを、文化史のうえでは桃山時代と呼んでいます。この変革期には、明るく開放的、豪華絢爛、斬新でエネルギッシュな文化が花開きました。 匠たちが、競ってたくみを凝らした時代です。 本展では大阪城天守閣が収蔵する絵画や蒔絵調度、染織工芸品、武具などのうちから、桃山美術の優品をお楽しみいただきます。」 ■ 桃山のTAKUMI -意匠・技巧・工匠 ■ 3月18日から5月7日まで開催 ■ 大阪城天守閣 : 大阪市中央区大阪城1番1号 06-6941-3044 http://www.osakacastle.net/specials/%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e%e5%b1%95%e3%80%80%e3%80%8c%e6%a1%83%e5%b1%b1%e3%81%aetakumi%e2%80%95%e6%84%8f%e5%8c%a0%e3%83%bb%e6%8a%80%e5%b7%a7%e3%83%bb%e5%b7%a5%e5%8c%a0%e2%80%95%e3%80%8d